奇妙な虚脱感のようなものがある。 馴染みのある感覚だ。知ってる。これは虚脱感ではない。 ――そうだ。これは、無力感だ。 彼女はきっと、もう、戻らない。 その事実が一人になってしまった静寂よりも、重く重く肩に圧し掛かってきた。 クッキーの包み紙。まだ温もりの残る紅茶。座っていた形のまま皺のついたソファ。先程まで彼女がいた場所を視界に入れることに耐え切れなくなって、自室に逃げ込んだ。この醜さをこの弱さを、幾分か隠してくれるような薄暗さに逃げた。 傷つけたのだろうか。 それとも。 それとも――――? 考えるのが億劫になる。 今は何も考えたくない。それなのにこの一人きりの家には、静寂しかなく、思考を阻むことのできる価値あるものなど見当たらない。 苛立ちが募ってゆく。 悶えるような苦しみが、鈍い痛みを伴ってやってくる。 そして、それらよりもずっと深いところから、もっと向こうから、湧き上がってくる憎悪。 苦しい。 苦しい。 此処は、苦しい。 「…………………………………っ…馬鹿が」 誰が? そんな問いは無意味だ。 どうしようもないことへの苛立ちが、衝動を燃え上がらせる。 何かに当たらずにはいられなくなって、机の上に積み上げられた書類という書類を腕で床に叩き落す。 そして、目に付いたのは。 置いたままにしておいた、銀色の懐中時計。相も変わらず、等しく時間を刻み続けるその存在。 激しい怒りが、背筋を這い登るように、色濃い気配を伴って全身を支配する。 銀色のそれを乱暴に鷲づかみにして、振り上げた。 手の平に、しっくりと馴染むその感覚に、腕が止まった。 (どの角度からどうやって見ても懐中時計ですね。まあ見方を変えれば、硬いから多少の凶器にもなるかと) 表面は、不思議にひんやりとしている。 (ヘソクリがパアさ) その温度が、まるでスポンジに水が滲みてゆくように、手の平から伝わる。 (でもわたし、アクセサリー1つくらいじゃ満足しない女だから) 雨が。 あの日、降っていた土砂降りの雨が。 (だから数年先か、数十年先か) 焔を、弱めて。 怒りを溶かして。 憎悪を包んで。 (またプレゼント貰いに行くよ) セブルス・スネイプという、どうしようもない男を、何度でもすくい上げてくれる。 その存在は今、支えを失った細い花の茎のように、不安定で、脆くて、危うい。 約束を覚えてる? どの約束だ? 最後の約束? それより前の? 否、それよりももっと前の? 最初の約束はなんだった? 指きりげんまん 嘘ついたら 針千本 飲ます 指切った 「……………………くそっ! あの馬鹿がっ!」 お前は何を求めてた? これで良かったのだ、と空を仰いだ。 降り始めたばかりの、霧雨が頬を濡らす。あの日のような土砂降りとは似ても似つかない、柔らかで、包むように優しい感触。 頬を伝い顎を伝い、滴り落ちる雫は、確かに雨でしかなく、涙でないのが不思議だった。 ぼんやりと、帰りのバスを待っている。動くのが億劫で、結局雨に濡れていくのを目を閉じて受け入れた。諦めは、心地よかった。薄手の服が、ゆっくりと冷たくなり、肌に張り付くのを目を閉じてじっと感じていた。 もう、いいんだ。 彼は拒まなかった。受け入れてくれた。 変わったところもある。変わっていないところもある。 傷つくまいとしてくれた。傷つけまいとしてくれた。 だから、もう、いいんだ。 これ以上彼を苦しめることに、何の価値があるというのだろう。 あいつは死んでなかった。 生きてて、ちゃんと、そこにいてくれた。 それでもう、十分だ。 雨粒が、瞑目する顔を、飾られない黒髪を、薄手の服を、泣かないを、ゆっくりとそして確実に濡らしてゆく。 結局のところ、わたしは弱くて。 臆病で。 本当は傷つける覚悟なんかなくて、傷つく覚悟さえなくて。 逃げてしまったんだ。温もりからも優しさからも。 悔しかった。けれど安堵もした。 顔を背けてしまえば、何も見ないですむことに気付いた。蹲ってしまえば、もう疲れないことにも気付いた。 だから。 だからもう、いい。 ふと、突然、雨が止んだ。 目を開けると、先程まで広がっていた曖昧な色の曇り空は見えなかった。自分めがけて落ちてくる水滴も見当たらなかった。 視界を覆っていたのは、黒い布地だった。 黒い無地の、傘の内側。 振り返ると、 「……お前やっぱり、雨やら雪やらでずぶ濡れになって、風邪を引くのに快感を感じる新手の変質者なんだろう」 古い――懐かしいくらい昔の下らない冗談を、真顔で言う男の、変わらない仏頂面。 呆れたような声は、よく知った響きだった。 「何か用?」 唇から零れ落ちた言葉は、自分でも驚くほど抑揚がなかった。 何をしている? 偽るのは得意だろう? 笑って誤魔化せば、隠し通せるはずだろう? 「言い忘れたことがあった」 傘からはみ出している彼の肩が、濡れて、黒い染みのようになっていく。 「言い忘れたこと?」 問い返す声は、真っ直ぐな彼の目に比べれば、苛立たしいほど頼りない。 掠れているわけではないのに、震えているわけではないのに、それは弱音のような響きに聞こえて、逃げ出してしまいたくなった。けれど、彼の目が、それをさせてくれなかった。 「私はお前を許さない」 息を呑んだ喉が、ひゅっと音を立てた。 今、自分はどんな顔をしているのだろう。彼の目にはどんな風に映っているのだろう。 それを確かめようと自分を見つめる黒い瞳の中に自分を懸命に探したけれど、結局それは見つからなかった。虚無のようなそれに、吸い込まれてしまったようだった。 「お前は私との約束を、一つとして守らなかった。そのことを、私は今も、まだ許せないでいる」 彼は相変わらず隠し事が上手くて、虚無のむこうに揺らめいているものの、その正体は分からない。 けれど。 「だから」 けれど彼の目は真っ直ぐで、 「全部、償え」 強くて、 「1つずつで構わない」 あたたかくて、 「すべての約束を果たせ」 嗚呼…どうして…、 「それまでは私は決してお前を許さない」 どうして、そんなに、どうしようもなく、優しいんだ。 「お前は………いつか、私に手を差し伸べつづけると言った。あれから、もう十数年が経つ。もしも、もしも、まだ間に合うのなら、―――いや、たとえ遅すぎるとしても。その行為が無価値同然になっていたとしても……っ」 それは、同情や哀れみでは決してない。 突き放すでもなく、慰めるでもなく、ただ、ただ、真っ直ぐで。 捻くれた言い方しかできない人間が、必死で、自分の中の“本当”を伝えようと、声を絞り出して。 「私は多くの罪を抱えたままだ。それを贖おうとは思わないから、一生抱えたままだろう。だからこの血塗れた手に、何が出来るかなど分からない。それでも、私は」 彼が自分の思いを、これほど言葉にしたことがあっただろうか。 ここまで正直になってくれたことが。 「お前を、もう一度失うのは、耐えられないっ」 虚無に見えた瞳の向こうにあるのは、悲しみとか、罪悪感とか、そんな、単純なものではなくて。 そう、そこには。 セブルス・スネイプという男がいた。 「だからせめて、誰にも話せないことを聞いてやる特権ぐらい、私に与えろ」 は、両拳をぎゅっと握り締めた。 ああ、もう耐えられそうもない。 「お前にもう一度約束を果たす機会をやったんだ、私にももう一度機会を寄越せ」 涙が。 「まさか、最初の約束を、忘れたわけではないだろう?」 溢れて。 彼の骨ばった手が伸びてきて、不器用にその涙を拭った。 大きな手だ。優しい手だ。 雨に濡れて冷たくとも、そこにはいのちの確かな温もりがあった。 「忘れたなぞとほざいたら、千本だか万本だか針を用意して、無理矢理にでもその口に流し込んでやる」 そんな古い――嗚呼、懐かしいくらい昔の下らない冗談を、そんな声で、こんなときに、真顔で言うから。 「………ッカヤロー…」 涙が、止まらないじゃないか。 苦しかった。寂しかった。悲しかった。辛くて辛くて、壊れてしまいたかった。本当は泣きたかった。でも泣き方が分からなかった。だからもっと苦しかった。息が詰まりそうだった。そのまま息ができなくなればいいのに、それでも呼吸はつづいてた。生きるってことが苦しくて、でもどこかで生きたいと願ってて、死のうなんて考えられなくて。募るのは罪悪感ばかりで。苦しくて。悲しくて。苦しくて。苦しくて。 あいたかった。 あまりにも頑丈すぎた堰を切ったのは、16の夏“下らない”と吐き捨てて柵を断ち切ってくれた拳と同じ、大きな手。 切られた堰から、押さえ込まれていた数多の激情が押し寄せてくる。あまりの激しさに体が震えて、一人では立っていられなかった。その場に崩れ落ち震える両手で顔を覆うよりはやく、視界は黒く塗りつぶされた。薬品の匂いが染みこんだそれに、どうしようもない懐かしさを押さえきれず、そのままぎゅっとしがみついて小さな子どものように泣いた。土砂降りの日に、土に吸い込まれて消えた雨も涙も、別れの歔欷も、すべてが報われたと感じた。差し伸べた傷だらけの手が、やっと届いたのだと。 いつかのように声を上げて泣き始めたの細さに、スネイプは抱きしめる腕に力を込めた。 白い悪夢の中で、何度伸ばしても届かなかった腕が、この小さな存在を抱き締めているという現実を確かめる。そして一ヶ月前ならば絶対に信じなかっただろうこの、それこそ夢のような現実に、目の奥が熱くなった。 もう、何があろうと、決して離しはしない。 固く、固く、固く胸に誓う。 神でも、月でも、星でもなく、この胸に燃える命に誓おう。 気がつけば、言いたくても言えなかった言葉を、何の抵抗もなく口にしていた。 「 おかえり 」 2005/10/19 完 結 ! おお、終わった! 終わったよ母ちゃん!(他に言うことはないのか) 始めたときは、「書き終わる前に挫折しそうだな〜」なんて暢気に思ってたこの長編が、 いつのまにか皆さんの声援を得て、いつのまにかこんな長い話になってて、 そして終わった。 すごい、とてもすごいことです。 今まで応援、本当にありがとうございました。 スロー更新に付き合ってくださって、本当に、心の底から嬉しかったです。 続編は、というと、やはり考えてはいます。 まだ計画の段階で話も全然出来上がってないので、あまり大きな声では言えないのですが、 次回は、「原作沿い」、というやつになりますか?(聞くな) それでは。 これからも、どうぞよろしくお願いいたします。 佐倉 (ワンドリサァチさんのランキングに参加してるので、良かったらポチッと一度投票してやってくださいv) |
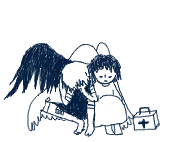 だいじょうぶ そばにいるよ ねえ、きみがすきだよ 泣いていいよ ここにいるよ |